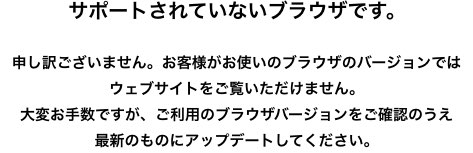|
琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究施設の和智仲是助教と北海道大学総合博物館の小西和彦資料部研究員は、これまで八重山諸島から記録のなかった寄生バチの一種・ホウネンタワラチビアメバチを西表島から報告しました。この研究は当時3歳の子の公園での「これ、なに?」が発見のきっかけになりました。 和智かの子氏(当時3歳)が、父親の和智助教と公園で虫取りをして遊んでいたときに、草むらの葉にぶらさがった不思議な模様をした繭を見つけました。和智助教がその繭を持ち帰り、後日羽化したハチの同定を小西研究員に依頼したところ、ホウネンタワラチビアメバチという寄生バチであることが分かりました。このハチは稲の害虫・フタオビコヤガなどの蛾の幼虫に寄生する種で、沖縄県ではこれまで多良間島からの記録しかなく、八重山諸島からの記録は今回が初めてのものです。 西表島は、その豊かな生物多様性が評価され、世界自然遺産に登録されました。しかし、今回の発見は必ずしも西表島だからこそできたものではありません。昆虫は非常に多様で、特に小型の種は名前のついた種を見つけるだけでも難しい場合があります。そのため、日本全国どこでも、公園のような身近な環境にも未発見の昆虫が数多く存在し、だれもが発見者になれる可能性を示しています。 本研究成果は 2024 年 12 月 30 日付で日本昆虫分類学会が発行する学術誌 Japanese Journal of Systematic Entomology に掲載されました。
|
<発表概要>
ヒメバチ科の寄生バチ・ホウネンタワラチビアメバチCharops bicolor (Szépligeti, 1906) は、オーストラリアからインド、東南アジア、中国、朝鮮半島、台湾などに広く分布し、日本では本州、四国、九州、沖縄(今までは多良間島のみ)から知られています(文献1)。また、この寄生バチは、本州、四国、九州では、稲の害虫であるフタオビコヤガなどの蛾の幼虫に寄生することが知られています。そして、沖縄県における唯一の記録は、普段はとても珍しい蛾の一種・アフリカシロナヨトウが多良間島や西表島、奄美大島、喜界島で大発生したときに、多良間島のアフリカシロナヨトウの幼虫から得られた個体に基づいていました(文献2)。
今回のハチの「発見者」である和智かの子氏は、西表島西部・うなり崎公園の散策路脇でイネ科植物の葉にぶら下がったもの(図1)を2つ見つけました。和智かの子氏はその時点ではこれがハチの繭(注1)であるとは認識していませんでしたが、和智助教は繭がヒメバチのものであることに気づき、研究室に持ち帰って成虫の羽化を待ちました。羽化したハチ(図2)の同定をヒメバチの分類の専門家である小西研究員に依頼したところ、沖縄県では多良間島からしか記録がなく、今回の発見は西表島だけでなく、八重山諸島からも初めての記録となるホウネンタワラチビアメバチであることが判明しました。
3歳の子供が研究者である親と公園で虫取りをして遊んでいた際に偶然見つけた繭が今回の発見のきっかけとなりました。その繭から羽化したハチは、八重山諸島で初めて記録される種であり、地域の生物多様性の一端を解明する重要な成果となります。この偶然の発見がなければ、今回の研究は成立しなかったといえます。今回、「これ、なに?」と思う好奇心が、研究や発見の出発点であることを3歳の子供から改めて教えられました。本研究に用いた全ての標本を見つけてくれたことに対して和智助教と小西研究員は深く感謝しています。

図1. ホウネンタワラチビアメバチの繭が見つかったイネ科植物と繭(右上)

図2. 西表島産ホウネンタワラチビアメバチのメス(上)とオス(下)
<今後の展望>
今回、繭が発見されたものの、西表島におけるこのハチがどの種の蛾の幼虫を利用しているのかは未解明のままです。注目すべき点として、ホウネンタワラチビアメバチがその幼虫を利用する主要な蛾として知られているフタオビコヤガは、南西諸島では屋久島、奄美大島、沖縄島、石垣島、与那国島から記録されていますが、西表島からは確認されていません(文献3)。また、このハチが寄生する種の一つであるアフリカシロナヨトウについても、かつて大発生が報告されたにもかかわらず、西表島でこのハチが得られた記録はありません(文献2)。このように、西表島では既知の寄主となる蛾が確認されていない点が、このハチの生態に関するさらなる解明の必要性を示唆しています。
これらの背景を踏まえ、本論文では西表島のホウネンタワラチビアメバチが利用している可能性のあるチョウやガを12種挙げています。その中には畑作物の害虫である蛾の一種・ハスモンヨトウのほか、稲の害虫も含まれています。実際このハチの寄主として畑や水田の害虫のチョウやガの仲間が多く記録されており、ホウネンタワラアメバチはもともと草原性の種であると考えられます。今後、草原での調査を重点的に行うことで、これまで見つかっていない南西諸島の他の島でもこのハチを採集できる可能性があると期待しています。
昆虫は非常に多様なため、西表島でなくても今回のような発見の可能性があります。特に小型の種については、名前がついた種を見つけることが難しい場合もあるほどで、「これ、なに?」と思う好奇心があれば、日本全国、どこでも、だれにでも新しい発見のチャンスがあります。今回の研究が、身近な生き物に興味を持ち、その多様性を観察するきっかけとなれば幸いです。
また、今回の研究は、小さな子供による身近な自然観察でも、科学研究に十分寄与できることを示し、生物多様性研究において年齢に関係なく幅広い参加が可能であることを示す好例でもあると考えています。今後も、島に住む研究者として、このような地域での発見を研究論文として形にすることに少しでも貢献したいと考えています。そして、機会があれば、地域の住民の方が同様の発見をした際、その成果発表を支援し、研究者として地域に貢献できるよう努めたいと考えています。
注1 寄生バチの仲間(主にヒメバチやコマユバチなど)には、幼虫が寄主の体内で成長し、蛹になるときに寄主の体外へ出て繭をつむぐ種が多くいます。
<参考文献>
1) 小西和彦・松本吏樹郎, 2020. ヒメバチ科. In. 日本昆虫目録編集委員会(編)日本昆虫目録, 第9巻 膜翅目, 第2部, 細腰亜目寄生蜂類.
2) 上里卓己・瑞慶山 浩・島谷真幸・山口綾子・兒玉博聖・渡嘉敷唯彰・若村定男, 2011. 琉球列島におけるアフリカシロナヨトウの大発生. 植物防疫, 65: 47–52.
3) 木村正明, 2020–2024. 琉球産蛾類目録 2020. https://gashowkimura.wixsite.com/website/moths-of-ryukyu
<論文情報>
-
論文名:New distributional record and list of potential hosts for Charops bicolor (Szépligeti, 1906) (Hymenoptera: Ichneumonidae: Campopleginae) from the Yaeyama Islands, Okinawa, Japan.
邦題名:八重山諸島からのホウネンタワラチビアメバチ(ハチ目:ヒメバチ科:チビアメバチ亜科)の初記録と寄主候補種の一覧 -
雑誌名:Japanese Journal of Systematic Entomology 30 (2) 284–292.
[目次情報] https://sites.google.com/site/jjsystent/old-volume/contents/vol-302
[文献情報] https://zoobank.org/References/1120D75D-D131-4AF5-82E8-42D3C94937AF注)zoobank: 動物命名に関する国際動物命名規約(ICZN: International Code of Zoological Nomenclature)のもとで、新たな命名行為、分類学的な著作物、および著者を公式に登録するためのオンラインデータベース
-
著者名:Nakatada WACHI* and Kazuhiko KONISHI
*: 責任著者