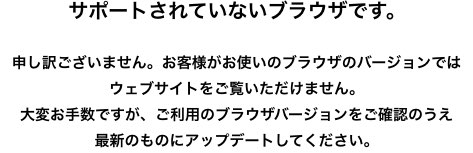|
琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究施設の和智 仲是 助教は、これまで西表島では見かけなかったカメムシをトイレの網戸で発見し、沖縄の動植物の生態や外来種問題に詳しい沖縄市立郷土博物館の刀禰 浩一(とね こういち)主任学芸員と協力してこのカメムシが北米原産のマツヘリカメムシであることを突き止めました。マツヘリカメムシはマツ科の針葉樹の種子などを加害する侵略的外来種で、世界中に拡散しています。日本では2008年に東京で初めて記録されて以降、急速に分布を広げており、北は北海道から南は沖縄県(沖縄本島)まで47都道府県中42都道府県での記録が確認されていました。八重山諸島ではこれまでに記録はなく、今回が初めての報告となります。 |
<発表概要>
マツ科の針葉樹の種子などを加害するマツヘリカメムシは、高い移動性をもつ侵略的外来種で、すでに侵入した地域からさらに別の地域へと拡散する「ブリッジヘッド・インベージョン」(注1)の典型例として知られ、世界各地に広がりつつあります(文献1)。実際、マツヘリカメムシの原産地である北アメリカ西部に代わって、北アメリカ東部が原ヨーロッパへの拡散源となったことが報告されています(文献1)。

図1. 西表島産マツヘリカメムシ。発見時の様子と標本写真(和智 仲是撮影)。
日本では2008年に東京都内で初めて確認されて以来、マツヘリカメムシは全国的に分布を拡大し、最新の調査(文献2)では47都道府県のうち滋賀、広島、高知、宮崎、鹿児島を除く42都道府県で記録が確認されています。さらに2019年には、海を越えた沖縄本島の沖縄市でも本種が初めて確認され(文献3)、県木であるリュウキュウマツへの潜在的脅威として、宮古・八重山地域への拡散も懸念されてきました。
2024年12月17日に、琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究施設の和智 助教は、施設内のトイレの網戸で本種を発見しました(図1)。これまで西表島だけでなく八重山諸島からも本種の報告がなかったことから、沖縄本島でのマツヘリカメムシの初記録を報告した著者の一人で、同島内の本種の分布に詳しい刀禰主任学芸員の協力のもと、iNaturalistやいきものログなどのインターネット上で閲覧可能な市民科学(注2)データを活用し、沖縄県を含む国内外の記録を整理・分析しました。
その結果、日本では、記録数が2020年代に急増しており、市民科学による観察数もこの時期に増加していることが明らかになりました。沖縄本島では、2019年に沖縄市で最初に記録され(文献3)、続いて2022年に名護市と国頭村で追加記録されています(文献4)。さらに、iNaturalistでは2021年と2023年に本島北部(恩納村)での観察が確認されました。近隣の海外では、ロシア(123件)、韓国(300件)、中国大陸(110件)、台湾(3件)、香港(4件)からの観察記録があり、いずれも2020年代以降に増加していました。
2024年12月時点で、市民科学プラットフォームには日本国内から計208件(iNaturalist:183件、いきものログ:25件)の観察が報告されており、その大半(202件)は本州からのものでした。いきものログに投稿された観察地はいずれも既に文献記録のある地域(青森、秋田、福島、新潟、石川、長野、埼玉、東京、神奈川、兵庫、和歌山、山梨)でしたが、iNaturalistでは、これまで記録がなかった滋賀、広島、鹿児島での新たな観察が確認されました。一方、2021年に四国の香川県(文献5)、2022年に北海道札幌市(文献6)で初めて記録されたにもかかわらず、市民科学プラットフォームにはこれらの地域からの報告が存在しませんでした。こうしたギャップは、市民科学データが文献記録を補完しうる一方で、情報に偏りがあることも示しています。
西表島への侵入経路としては、本州・九州、沖縄本島、台湾など複数の可能性が考えられますが、地理的近さや近年の記録から台湾からの飛来が最も可能性が高いと推察されます。なお、本種は光に誘引され、ライトトラップでも得られていますが、発見地点付近で継続実施されているライトトラップやマレーズトラップでは確認されておらず、偶産(本来の棲息地からかけ離れた場所で偶然に見つかったこと)である可能性も否定できません。今後、西表島における本種の定着状況や拡散リスクを継続的に監視することが、リュウキュウマツを含む島の生態系の保全において重要です。
<今後の展望>
本研究では、日本各地におけるマツヘリカメムシの分布記録を整理し、その拡大傾向を明らかにしました。
マツヘリカメムシは現在、環境省の「定着初期・限定分布」に分類(文献7)されていますが、本研究の結果は、既にその段階を超えて全国的に定着・拡散が進行している可能性を示しています。本研究で確認されたiNaturalistの約200件におよぶ観察記録、文献では報告されていないと思われる滋賀・広島・鹿児島での新たな県レベルの新産記録、さらに中国大陸・台湾・香港での近年の観察例は、本種の外来種としての評価や今後のモニタリングの方針を決める上で重要な知見であると考えられます。
日本国内における本種の分布状況や記録のばらつき、観察時期の違いなどから、全国への侵入経路は単一ではなく、複数の独立した経路が存在した可能性が高いと考えられます。本種の分布拡大の背景には、貨物輸送や人の移動といった人為的要因が関与している可能性が高く、今後は分子生態学的解析や標本の比較を通じて、侵入の由来や拡散経路の特定を進めていく必要があります。西表島への侵入経路については、地理的に近く、近年の観察記録も確認されていることから、台湾が有力な侵入源と推定されますが、沖縄県ではこれまでにも外来昆虫が数多く確認され、その多くは日本の九州以北に由来することが知られています。また、沖縄本島で確認されている一部の種については、米軍基地との関連も指摘されており、沖縄本島の本種についても、分布パターンや高密度地点の偏在性などからその可能性を慎重に検討する必要があります。
さらに、現在の本種に関する多くの記録は、地方の昆虫同好会の会誌や紙媒体のみの商業誌に依存しており、国際的な生物多様性情報(例えば、GBIF(注3))には十分に反映されていません。地方の昆虫同好会誌には、各地の自然愛好家や在野の研究者によって観察・報告された貴重な分布記録が多数掲載されており、地域に根ざしたかけがえのない一次情報である一方で、こうした記録の多くは紙媒体で発行され、限られた範囲でしか共有されていないため、情報が埋もれやすいのが現状です。加えて、記録の様式に統一性がなく、査読体制もないことが多いため、科学的な利活用には一定の限界があります。このため、本種のような外来種の効率的なモニタリングには、記録の収集と共有を促進する体制の整備が急務です。市民科学プラットフォームは、早期発見と分布動態の把握に有効であり、また専門家によるチェックが行われている場合もあることから、今後の外来種対策における重要な情報源として活用できるのではないでしょうか。とくに沖縄県では、定着初期または偶産と考えられる段階にある本種の動向を把握するため、市民科学による継続的な監視が有効な手段になると信じています。
<用語解説>
(注1)ブリッジヘッド・インベージョン(Bridgehead invasion):外来種が原産地とは異なる地域に一度侵入・定着した後、その定着地を起点としてさらに別の地域へ二次的に拡散する現象を指す。これは、侵入先の一部の個体群(=ブリッジヘッド集団)が中継拠点のような役割を果たし、そこからさらに新しい地域へと移動・定着することで、侵入の連鎖が加速していく、いわば「侵入がさらなる侵入を生む」自己増幅的な過程である(文献8)。この現象は、侵略的外来種が広範囲に急速に分布を拡大する背景の一つとして注目されており、特に人為的な輸送ネットワークの構造と結びついて発生することが多いとされる(文献8)。
(注2)市民科学(Citizen Science):科学研究に、研究を専門としていない人々が直接参加すること。参加者は、職業として研究に従事する科学者(職業科学者)と対比して「市民科学者」とも呼ばれる。こうした研究は、通常、職業科学者や学術研究機関の指導のもとで行われ、市民科学者はボランティアとしてデータの収集や、得られた結果の分析・考察にかかわる。近年では、SNSや専用プラットフォームを通じて世界中からの参加者を募るものも増えており、本研究で参照したiNaturalist やいきものログもそうした事例にあたる。
iNaturalist: https://www.inaturalist.org/
いきものログ https://ikilog.biodic.go.jp/
(注3)GBIF(地球規模生物多様性情報機構, Global Biodiversity Information Facility):世界中の生き物の「いつ・どこで・何が見つかったか」といった情報を、誰でも自由に利用できる形で公開している国際的なデータ共有ネットワーク。各国の政府や研究機関が参加しており、博物館の標本データや、市民による観察記録、最新のDNAデータなど、さまざまな情報が集められている。GBIFに登録された情報は、共通のルールや形式で整理されており、研究者だけでなく、環境保全や政策立案などさまざまな分野で活用されている。オープンアクセスであるため、誰でも無料でアクセスでき、世界の生物多様性を「見える化」する重要な仕組みとなっている。(https://www.gbif.org/ja/what-is-gbif を参考に文章を作成しました)
<参考文献>
1. Lesieur, V., E. Lombaert, T. Guillemaud, B. Courtial, W. Strong, A. Roques & M. A. Auger-Rozenberg, 2019. The rapid spread of Leptoglossus occidentalis in Europe: a bridgehead invasion. Journal of Pest Science, 92: 189–200.
2. 岩田朋文, 2024. 富山県におけるマツヘリカメムシの初記録. 富山市科学博物館研究報告, 48: 41–45.
3. 刀禰浩一, 大城哲也, 2020. 沖縄島で外来種マツヘリカメムシLeptoglossus occidentalis Heidemannを確認 (Hemiptera: Coreidae). 琉球の昆虫, 44: 79–80.
4. 後藤健志, 後藤健太郎, 2023. 沖縄島北部で確認されたマツヘリカメムシ Leptoglossus occidentalis Heidemann の記録. Pulex, 102: 972–973.
5. 玉川晋二郎, 田村茉織, 安森盟文, 2022. 香川県におけるマツヘリカメムシの記録. 月刊むし, 613: 32–33.
6. 佐々木柊太朗, 2023. 北海道におけるマツヘリカメムシの初記録. 月刊むし, 625: 45.
7. 環境省・令和6年度, 第3回, 生態系被害防止外来種リストの見直しに係る検討会, 資料3-3:リスト加除対象の候補種一覧<動物> https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist/gairailist/byseitailist3/shiryou3-3.pdf
8. Bertelsmeier, C., & L. Keller, 2018. Bridgehead effects and role of adaptive evolution in invasive populations. Trends in Ecology & Evolution, 33: 527–534.
<論文情報>
- 論文名:Occurrence of the invasive western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Coreidae) in Iriomote Island, the Yaeyama Islands, Japan and inference of its sources based on the literature and citizen science records
- 雑誌名:Japanese Journal of Systematic Entomology, 31 (1): 80–84.
- 著者名:Nakatada Wachi*, Koichi Tone
*: 責任著者 - DOI:https://doi.org/10.69343/jjsystent.31.1_80