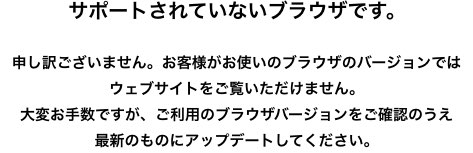|
神戸大学大学院人間発達環境学研究科の内山愉太助教および琉球大学医学部保健学科の喜屋武享准教授らの研究グループは、日本の大都市圏に居住する3,500名を対象に、客観的な自然との関係(自然訪問頻度や居住地周辺の自然度)と、主観的な自然とのつながり(自然への親近感や幼少期の自然体験)を調査し、居住地区の困窮度や都市化の程度も分析に加えることで、都市化度と困窮度の高い地区では自然訪問頻度と健康(主観評価)とのつながりが最も強いこと等を明らかにしました。 |
 研究対象地に含まれる近畿圏の都市緑地
研究対象地に含まれる近畿圏の都市緑地
ポイント
-
自然との客観的・主観的関係性(訪問頻度や親近感)は、都市住民のウェルビーイングとポジティブな関連性がある。
-
社会経済的な困窮度の高い地区では、自然へのアクセスが住民の健康にとって特に重要であることが判明。
-
困窮度の低い地区では自然への親近感が生活満足度と関連が強い傾向を把握。
-
居住地区の困窮度や都市化度に関わらず、幼少期の自然体験の度合いは成人の主観的健康観と関連性があることを特定。
-
居住地区の都市化度や困窮度等の状況に即した緑地・水辺整備や自然体験の充実は、都市における健康格差の縮小に寄与する可能性がある。
研究の背景
現代の都市生活では、自然とのつながりが人々のウェルビーイング(心身の健康や生活満足度等)に与える影響が注目されています。しかし、自然へのアクセスには居住地区ごとの格差が存在し、特に社会的・経済的に困難な地区では、自然に触れる頻度が少ない傾向があるなど居住地区によって自然へのアクセスや感じられ方等には差異があり、こうした「自然との関係性の格差」は、健康や幸福の不平等につながる可能性があります。これまでの研究では、居住地区レベルの分析が不足しており、個人や世帯レベルの分析が主流でした。自然アクセスの格差の影響の深刻さが把握されていく中で、個人や世帯を対象とした政策・取組だけでなく、都市計画的な観点からも緑地・水辺の整備等の対応を行う際のエビデンスが必要とされていました。そのニーズに対応すべく本研究では居住地区レベルの困窮度も考慮した分析を行いました。
本研究においては、日本の代表的な大都市圏である東京・横浜圏と大阪・神戸圏に居住する3,500名を対象に、客観的な自然との関係(自然訪問頻度や居住地周辺の自然度)と、主観的な自然とのつながり(自然への親近感や幼少期の自然体験)を調査し、居住地区の困窮度や都市化の程度も分析に加えることで、都市においてどのような種類の「自然とのつながり」がどのような地区で必要とされているのかを明らかにしました。本研究は、格差のある都市環境において誰もが自然とつながり、健康で充実した生活を送るための具体的な施策の立案に貢献することを目指しています。
研究の内容
本研究では、「客観的な自然との関係性」(自然を訪れる頻度や住環境における自然の多さ)と「主観的な自然とのつながり」(自然への親近感や幼少期の自然体験)という2つの側面から自然との関係性を評価しました。さらに、地域の「困窮度」(地理的剥奪指標※1)や「都市化の程度」(居住地区内の市街地の割合)といった居住環境要因、そして市民参加や地域愛着といった社会的要素も加え、多変量解析によってそれぞれが人々のウェルビーイングとどのように関連するかを検討しました。
本研究のユニークな点は、①自然との関係性を客観・主観の両面から同時に扱った点、②都市化や地域困窮度といった地理的・社会経済的条件を組み合わせて分析した点、③子ども時代の自然体験と成人の健康の関連性を解析した点、④社会的つながり(ソーシャルキャピタル)の影響を考慮した多層的な解析を行った点です。さらに、アジアのメガシティにおける大規模調査であることも、これまで欧米中心だった研究に対して新たな知見を提供しています。
本研究の具体的な成果としては、まず、自然との関係性が都市住民のウェルビーイング(心身の健康や生活満足度等)に関連することを特定し、都市化度の高い地区では、その関連性が全体的に強い傾向が把握されました。その中でも特に社会経済的な困窮度の高い地区では自然訪問頻度等の客観的な自然との関係が健康にとって重要であることを解明しました。また、困窮度の低い地区では自然への親近感等の主観的な自然とのつながりと生活満足度との関連が強いことを明らかにしました。幼少期の自然体験については居住地区の困窮度や都市化度に関わらず健康と関連することが把握されました。
これらの結果から、都市化度の高い地区では自然が貴重である度合いが高く、自然とのつながりを持つことが、ウェルビーイングに強く影響することが想定されます。また、困窮度の高い地区では、健康を高める方法の選択肢が相対的に少なく、身近な自然への訪問の重要度が高いため、自然訪問と健康の関連が比較的強いと考えられます。さらに、自然への親近感等の主観的な自然とのつながりが生活満足度に寄与するには、生活満足度を下げる困窮度等が低いことが条件となると予想されます。幼少期の自然体験は、ライフスタイル全体において健康的な選択肢を選ぶことと関連があると想定されます。
本成果は、限られた自然環境整備の予算を都市内各地区にいかに配分するか検討する際の基盤情報になり得ます。また、地域の環境や社会経済的な特性に根ざした自然体験の機会創出、都市緑地の整備・保全、そして健康政策立案に役立つことが期待されます。特に、日本では、都市内および都市近郊の緑地(都市林や農地等)や里山等を活用していくことが重要です。
今後の展開
本研究は自然との関係性と都市住民のウェルビーイングとの関連を明らかにしましたが、今後はさらに因果関係の解明や地域ごとの具体的な介入策の検討が求められます。たとえば、自然との関係性を高める動機や目的(健康や社会的な交流等)、利用される自然空間の具体的なタイプ(緑地・水辺、植生の種類や分布、生物の存在、人々の交流のあり方等)など、背景要因の詳細な分析が重要です。また、今後は時系列データや移動履歴(日常生活における移動や引っ越しなどによる移動を含む)を用いた追跡研究により、生活環境やライフコースの変化とウェルビーイングの関係を捉える必要があります。さらに、オンライン調査に伴うバイアスを補うため、郵送調査やインタビューの導入も検討の余地があります。加えて、日本の都市で得られた知見を、他のアジアの都市にも広げて比較することで、文化や環境の違いをふまえた実践的な政策提言にもつながっていくことが期待されます。現在、日本に加えてフィリピンとタイの都市を対象にした研究も国際機関から支援を受けて進めています。
用語解説
※1 地理的剥奪指標:居住地区の高齢単身世帯の割合や失業率などの指標を基に地域の困窮している度合いを推計する指標。日本では中谷友樹教授(東北大学)らの研究がある。
謝辞
本研究は、科研費プロジェクト(JP22H03813; JP22H03852; JP23H03605; JP23H03608)、環境研究総合推進費(1FS-2201)、Asia-Pacific Network for Global Change Research(CRRP2023-10MY-Uchiyama)の支援を受けて実施しました。
共同研究グループ
- 神戸大学大学院人間発達環境学研究科
内山愉太助教、佐藤真行教授、丑丸敦史教授、源利文教授、原田和弘教授、清野未恵子准教授、打田篤彦助教、佐賀達矢助教、山本健太助教 - 琉球大学医学部保健学科
喜屋武享准教授、高倉実名誉教授(現:名桜大学 特任教授) - 東京大学大学院農学生命科学研究科
香坂玲教授 - 南山大学総合政策学部
鶴見哲也教授
論文情報
- タイトル:Association between objective and subjective relatedness to nature and human well-being: key factors for residents and possible measures for inequality in Japan’s megacities
- DOI:10.1016/j.landurbplan.2025.105377
- 著者:Yuta Uchiyama, Akira Kyan, Masayuki Sato, Atushi Ushimaru, Toshifumi Minamoto, Kazuhiro Harada, Minoru Takakura, Ryo Kohsaka, Mieko Kiyono, Tetsuya Tsurumi, Atsuhiko Uchida, Tatsuya Saga, and Kenta Yamamoto
- 掲載誌:Landscape and Urban Planning