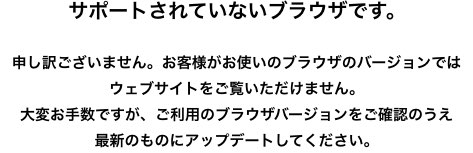|
琉球大学理学部ライマー教授らの研究チームによる研究成果が、海洋生物学の学術雑誌「Marine Biodiversity」誌に掲載されました。 |
<発表のポイント>
ライマー教授らの研究チームは、南日本の海山において非常に大型で寿命が長いと推定されるツノサンゴ目サンゴの群体を発見しました。この研究成果は、南日本の海山がこのような生物資源の保全に重要であることを示しています。
- 2020年に実施した海洋研究開発機構(JAMSTEC)の調査航海中に、日本南部の海山で、約525メートルの深さにある巨大なツノサンゴ類Leiopathes属の群体を発見しました。この群体は幅4.4メートル、高さ3.1メートル、基部の直径は28センチメートルでした。
- このツノサンゴ類の成長速度は非常に遅く、大きさから群体の年齢は約7,000年と推定しました。この結果は、ツノサンゴ類が地球上で最も長寿な生物の一つである可能性を示しています。
- こうした成長の遅い「生きた宝」の保全が、早急に必要です。
- なお本研究は海洋研究開発機構が実施した環境省からの委託事業「令和2年度沖合海底自然環境保全地域調査等業務」による成果です。

<発表概要>
琉球大学、海洋研究開発機構の研究チームを中心とする国際的な研究グループが、2020年12月に実施した深海調査において、北西太平洋の西マリアナ海嶺の沖合海底自然環境保全地域で、約7,000年生きていると推定される巨大なツノサンゴ目注1のサンゴ(黒珊瑚)の群体を発見しました。この発見は、深海生態系の理解や海洋保護区の保全に向けた重要な一歩となります。なお本研究は海洋研究開発機構が実施した環境省からの委託事業「令和2年度沖合海底自然環境保全地域調査等業務」による成果です。
研究の背景
令和2年に制定された沖合海底自然環境保全地域のうち、西マリアナ海嶺・中マリアナ海嶺北部海域には多数の海山が存在し、多様な海洋生物が集まる重要な生態系の拠点となっています。特に、ツノサンゴ類を含む大型の刺胞動物は、生物多様性の高いベントス(底生生物)注2群集の基盤を形成し、深海の「海洋動物の森」として知られています。しかし、これらの生物の多様性は十分に把握されておらず、また保護は不十分であり、持続可能な資源利用の観点からも、さらなる研究と保全が求められてきました。
研究内容
研究チームは、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の海底広域研究船「かいめい」とその搭載機器である無人探査機「KM-ROV」を用い、西マリアナ海嶺の525メートルの深海で、通常の数倍のサイズを持つツノサンゴ類の一種 Leiopathes cf. annosa の巨大な群体を発見しました。この群体は高さ約308 cm、幅441 cm、基部の直径が28 cmに達し、過去の研究による推定成長速度(0.02 mm/年)を基に計算すると、その年齢は約7,000年に達するものと推定されました。これにより、この群体は、地球上で最も長寿の海洋生物の一つである可能性を示しました。
社会的意義と今後の展望
今回の発見は、ツノサンゴ類のような長寿命な生物を含む深海の生態系において、いったん生物が失われてしまった場合、生態系の回復に非常に長い時間がかかることを示しています。この群体は、多数の共生生物を含み、深海の生物多様性の「ホットスポット」として機能しています。研究チームは、「この発見が、海洋保護区の適切な管理や、違法漁業からの保護に向けた対策を強化する重要な契機になる」としています。特に、日本政府が2020年に設定した沖合海底自然環境保全地域の管理と連携し、この地域の生態系保護に向けた具体的な行動が期待されます。
研究チームは今後も、他の海山で同様の調査を続け、さらなるサンプル・データ収集を行い、海洋生態系の保全活動と持続可能な深海資源利用に資する予定です。
用語解説
ツノサンゴ目(注1):黒珊瑚、深海に生息し、非常に長い寿命を持つことが知られている。
ベントス(注2):海底に生息する生物群集を指す。
<論文情報>
- 論文タイトル:A massive and ancient antipatharian colony at a seamount in the Northwest Pacific
(北西太平洋の海山にある巨大で長寿命のツノサンゴ目サンゴの群体) - 雑誌名:Marine Biodiversity
- 著者:James Davis Reimer*1,2, Kensuke Yanagi3, Guillermo Mironenko Castelló1, Kurt Bryant B. Bacharo1, Hiroyuki Yokooka4, Keita Koeda1, Shinji Tsuchida5, Yoshihiro Fujiwara5(*責任著者)
- 所属:1琉球大学理工学研究科、2琉球大学熱帯生物圏研究センター、3千葉県立中央博物館分館海の博物館、4いであ株式会社、5海洋研究開発機構
- DOI番号:10.1007/s12526-024-01478-w
- URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s12526-024-01478-w#additional-information